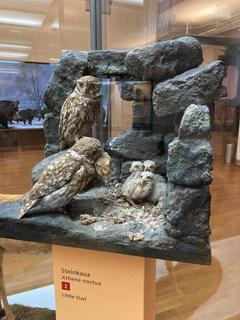ヨーロッパの大学院に留学してみた ②フランスでの生活
フランスでの生活を一言で表すなら、暗黒時代だ。中二病みたいなことを言っていると思うがウルトラスーパーダークナイトメアという気持ちで日々を過ごしていた。
さて、すべてがわからない。文字通り、すべてである。スーパーの買い物の仕方、洗濯機の使い方、交通機関の乗り方。銀行口座を作ろうにも予約の取り方がわからないし、ようやく銀行にたどり着いたと思えば銀行のドアは閉まっていて入れない(後に、ブザーを押せば開けてもらえることが判明した)。とにかく本当に些細なことで何度も躓いて何一つ予定通りに進まないので自分に嫌気がさした。
授業が始まると強いフレンチアクセントの英語に、そしてグループワークに苦しんだ。毎週の成績は最低ライン。自分だけなら良いが、グループでは私の拙い英語のせいで皆の足を引っ張っているのがとても苦痛だった。クラスメートは7割方フランス人で、留学生もヨーロッパ圏から来た英語が超堪能な優秀な人ばかり。皆母国語で講師とディスカッションができたし、そうでなくても英語で素晴らしいプレゼンテーションやエッセイを披露した。自分にはどちらもできなかった。
カルチャーショックにも苦しんだ。道路の状況や食品管理など、潔癖症の日本人が見たら気が狂いそうな違いだった。複数人の会話では他人の話に割り込むくらいの勢いで話さないと、何時間たっても発言の機会は一向に回ってこない。そして彼らはお酒をよく飲んだ。授業は9時から18時まであってそのあと課題をこなしていたら一日が終わるはずなのに、クラスメートは毎日のように夜の街に繰り出していた。その余裕とお金は一体どこから出てくるのか!
私は黒い虫がたくさん出るかつ北向きという条件の悪い部屋に住んでいたことも重なって、日照時間が短くなるとともに私のライフも削られていった。
1.5週間くらいの長期休暇があったので、気分転換に地中海沿いの街へ行ってみた。波の音を聞きながら紺碧に透き通った地中海と空を眺めていると、心が洗われる気がした。もうずっと一生このまま海を見ているだけでもよい。夢心地な地中海の誘惑であった。しかし目が覚めると、今度は勉強や課題をしていない自分の状況により焦ってしまって結局逆効果だった。
そんな私の精神に重くのしかかってきたのはインターンシップの受入先探しだった。私のコースでは、修了要件として、世界中どこの生物音響学の研究室でもよいから6か月間インターンとして働いてそこで修士論文を書いてきなさい、となっていた。しかし、まずもってどうやって受入れ先を探せば良いかもわからない。面白そうだと思った研究者に必死なメールを送ってみたが、研究資金も業績もない学生を誰が受け入れてくれるというのか。7割方無視されるか断られた。前向きな返事をくださった先生方も数人いたが、はっきりとした返事はまだもらえていなかった。一方で周りのクラスメートは南アフリカやらカリフォルニアやらスペインやらに行く準備をし始めていて、私は焦りを感じていた。
そこで私を救ってくださったのはまたしても相馬先生だった。先生の紹介のおかげで運良く、私はドイツのマックスプランク鳥類学研究所にインターン先を見つけることができた。まるで空から垂れてきた蜘蛛の糸であった。また私は相馬先生のお世話になってしまった。自分の力なさに呆れた。しかし、どうにもならない時には、助けを求めれることも大事だ。このご恩はこれから研究を頑張ってお返ししなければならない。
そして12月のどんよりしたフランスに、救世主のごとく颯爽と現れたのは、休暇にいらしていた太田菜央(マックスプランク鳥類学研究所)さん。同じ研究分野の先輩と母国語で話せるというのはなんとありがたいことか。この時私は数か月ぶりに対面で日本語を話したので、非常に変な感じがした。内容が同じでも、英語で話すのと日本語で話すのとでは得られる充足感が全く違う。思っていることを思うままの表現を用いて吐き出せる。自分の意図した話のオチのところで相手も笑ってくれる。なんて話しやすいんだ!太田さんの優しい人柄も大いに関係していると思うが、会話のノリというか、同じ文化のバックグラウンドをもっているというのは会話において意外と重要な要素かもしれない。太田さんとはドイツでまた会いましょうということでその場を別れた。
クリスマス直前、五藤を乗せた列車はイルミネーションの輝くサンテティエンヌの街を後にした。彼女はフランスの大学での授業の単位を取り終えたので、ドイツでのインターンシップに向かうのだ。新しい環境に不安そうな顔をしているかのように見えるが、どうやら頭の中はキラキラふわふわしたものでいっぱいだ。どうせクリスマスマーケットのことしか考えていないのだろう。全くのんきなことである。
だがもうこれでウルトラスーパーダークナイトメアにはAdieu!