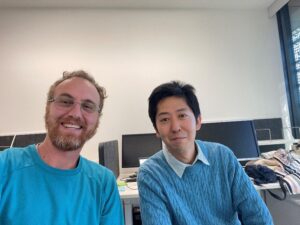【連載】家族4人で研究留学 in オーストラリア(5)素晴らしきオーストラリア
片山直樹(農研機構 農業環境研究部門 農業生態系管理研究領域)
熊田那央(バードリサーチ嘱託研究員)
皆さま、こんにちは。オーストラリア生活についての連載ブログも、いよいよ最終回となります。そこで今回は、片山と熊田それぞれにとって、特に思い出に残った出来事をお話ししたいと思います。いつもより少しだけ長めですが、お付き合いいただければ幸いです。
片山にとって最も印象的だったのは、研究発表と水田視察のために、ニューサウスウェールズ州のリバリーナ(Riverina)という地域を訪れたことです。オーストラリアでも稲作は行われており、その生産量の9割以上をリバリーナとその周辺地域が担っています。ちなみに、オーストラリアで約百年前に初めて稲作を成功させたのは高須賀穣という日本人の方です。詳しくはこちら:https://www.sunricejapan.jp/takasuka.html
リバリーナはオーストラリアの東南に位置し、メルボルンから約450km内陸に向かった先にあります。私はメルボルン空港でレンタカーを借りると、丸一日のロードトリップをスタートさせました。オーストラリアはスピード違反に対して非常に厳しく、あちこちに自動撮影カメラが設置され、制限速度を数キロでも超えると数万円またはそれ以上の罰金となります。私は安全第一で、何度も休憩を挟みつつ運転しました。道中にはエミューがいて、旅に刺激を与えてくれました。夜8時を回ると日が沈みだしますが、同時にカンガルーなどの野生動物が活発になります。彼らが道路に飛び出してこないかどうか、さらに神経を使うことになります。無事に宿に到着した私は、疲れきってすぐに寝てしまいました。

翌日、私はMatthew Herring博士(以下、マシュー)と再会しました。リバリーナの日中は40度を超えることもあり、涼しくなる夕方に水田地帯を案内してもらいました。この地域の湿地や田んぼには、世界でも約三千個体しかいないとされるAustralasian Bitternが繁殖しています。マシューは、彼らの生態を研究し、保全のために稲作農家と様々な取組みを進めてきました。繁殖に適したタイミングの水張りや、畔の草を刈り残すなどの工夫をしています。彼はなんと、数百件以上の農家の連絡先を知っているそうです! 許可なく農道には入れないため、彼があらかじめ農家の方に電話をして許可を取ってくれました。
夕暮れ、マシューは私をある場所に案内してくれました。そこにはAustralasian Bitternに配慮した田んぼがありました。美しい夕焼け空の下、一羽が田んぼから頭部を少しだけ出して、ボォーっと鳴きました。マシューの論文でしか知らなかった鳥の姿と鳴き声を、この目と耳で感じることができました。こんな美しい光景を見せてくれたマシューと農家の方々に、私は何を返せばよいのだろうかと思いました。

マシューは、現地での研究発表を企画してくれました。リバリーナには、オーストラリアのお米を製造・販売する「SunRice社」のオフィスがあります。そこで講演する機会をいただき、セミナーを通じて社員の方や研究者の方と交流することができました。色々な質問をいただきましたが、特に印象的だったのは「人口が減り続ける日本で、米の生産と生物多様性保全をどうやって維持できるのか?」というものでした。耕作放棄地の湿地化など、いくつかの可能性はありますが、まだ断言できるようなエビデンスは少ないです。私は今後の宿題とさせてもらいつつ、一刻も早く研究を進めなければならないと感じました。

こうしてリバリーナでの日々は、あっという間に終わりました。私はマシューとハグをして別れを告げると、後ろ髪を引かれる思いで最寄りのグリフィス空港に向かいました。彼と過ごした三日間は、オーストラリアでもっとも思い出に残る日々になりました。

熊田からは旅先で見られて興奮した鳥3選と大学でのセミナー発表について紹介します。ブリスベンを離れてケアンズ、タスマニア、ラミントン国立公園など、様々な場所を訪れ10年分くらいの旅行を1年で行ってしまった気分ですが、どこも本当に行ってよかったです。11月に訪れたケアンズでは、せっかくだからと現地在住の松井さんにガイドをお願いして1日たっぷりと鳥見に連れて行ってもらいました。子連れであれこれお願いしたにもかかわらずさすがプロ、季節的に少し早いラケットシラオカワセミを始め、鳥のリクエストにもしっかり応えていただいた上に子供たちが喜ぶ場所もおさえて大変充実した鳥見ができました。ありがとうございました。ケアンズで特に印象に残ったのがヒクイドリです。松井さんと別れた翌日、教えてもらったポイントに向かう途中の道で電線に止まるモリショウビンを見つけて車を停めて見ていたところ木陰に動く影が。よく見るとそこに子連れのヒクイドリの雄がいました。縞々模様のヒナ二匹と親が木の実を啄むところを子供達とじっくりと見、その恐竜っぽさにみんなで大興奮しました。

タスマニアではどうしても見たい鳥がいました。ムナジロウです。オーストラリア南部だけに生息するこのウを、メルボルンで見ることが叶わなかった私は、タスマニアでなんとしても見なければと意気込んでいました。初日の浜辺でその願いはあっさり叶います。オーストラリアシロカツオドリやミナミオオセグロカモメが遠くを飛んでいくのを眺めていると、海にうかぶウのシルエット。あれは!と思い見ると白黒ボディに黒い顔、間違いありません。その時は距離も遠くほんの短い時間の邂逅となりましたが、翌日にのったクルーズツアーではじっくり見ることができました。風の強い日で舟は大変揺れ、酔い止めを忘れて双眼鏡を覗きすぎてもう船酔いでへろへろではありましたが、だからこそ糞で白くよごれた岩とそこに集う群れは大変印象に残っています。

最後はラミントン国立公園でみたアルバートコトドリです。オスのダンスと鳴き真似が有名な種ですが、私たちが行った2月はあまり活性が高くないようで声もたまに聞こえるぐらい。見るのは難しいかなと思いつつ諦めきれずにトレイルを歩きまわり続けていましたが、旅程の最終日についに見ることができました。なによりも嬉しかったのが最近急速に鳥に興味を持ち出した長女が、宿に飾ってある絵を見てこの鳥がみたい!と言い出し頑張って歩き回り探した鳥を一緒に見ることができたことです。朝の4時から歩き通しても空振りした日の翌日にも、あきらめずにまた早朝からついてくる姿にオーストラリア滞在での成長を感じました。
研究関連の話も1つ。片山さんが昨年5月に行っていたクイーンズランド大のセミナーで、私も2月に発表させていただきました。メインは福島第一原発事故での避難指示区域での鳥類相の変化に関しての紹介をさせていただきましたが、もちろんカワウへの愛もアピール。いまいち伝わったかはわからないですが……。自分の研究で来たわけではないとはいえ、せっかく関連したテーマの研究室なのだからともらった機会。なかなか準備の時間もとれず慣れない英語発表に四苦八苦し、と大変ではありましたが、普段と違う人に聞いてもらい、質問してもらうというのはやっぱり大事だなあとオーストラリアで忘れかけていた研究モードに久しぶりになれ、本当にありがたい時間でした。発表機会を提供してくれ、如何ともし難い質疑応答をフォローしてくれた天野さんをはじめ、準備の時間を少しでも増やそうと家事育児を代わってくれた片山さん、発表練習につきあってくれたピアーズさんとそのご家族、本当に皆さんに感謝です。

振り返ってみると、日本を離れる時には全く想像もしていなかった、たくさんの素晴らしい出来事がありました。美しい自然の中での、鳥たちとの出会い。そして何よりもうれしかったのは、多くの親切な人たちとの出会いです。道ばたで話しかけてくれた、日本好きのピアーズさん。彼のお母さんで、私たちにテニスを教えてくれたペニー。教会で出会ってから、何度も鳥見に連れて行ってくれたウォーウィックとウェンディ。オーストラリアの田んぼを案内してくれたマシュー。そして私たちの研究も生活もサポートしてくれた、天野さんとそのご家族。私たちがこんなにもオーストラリアを好きになったのは、間違いなく彼らのおかげです。日本に帰国してからも、彼らとの日々を思い出すたび、私たちはオーストラリアを恋しく思うでしょう。
もちろん見知らぬ土地での暮らしは、楽しいことばかりではありませんでした。子どもたちには、日本とは全く異なる環境で日本語も通じない中、苦労させてしまいました。最後までがんばってくれて、本当にありがとう。いつかこの日々が、あなたたちの人生の糧になりますように。みんなで過ごしたこの一年は、私たちの人生の宝物です。
最後までこのブログをご覧くださった皆様、鳥学通信担当の皆様、本当にありがとうございました。