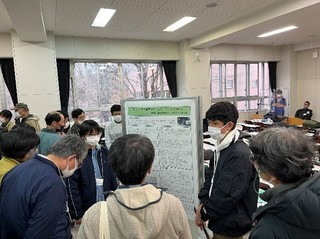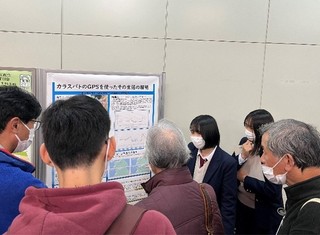第6回日本鳥学会ポスター賞「行動・進化・形態・生理」部門を受賞して
この度、日本鳥学会2022年度大会において「行動・進化・形態・生理」部門のポスター賞を授与して頂き誠にありがとうございました。
終始熱心なご指導を頂いた千葉大学機能生態研究室の村上正志教授に感謝の意を表します。また、実験の実施にあたり、千葉大学生物機械工学研究室劉浩教授、日本野鳥の会十勝支部室瀬秋宏様、行徳野鳥観察舎友人会佐藤達夫様、久米島ホタル館佐藤文保様、山階鳥類研究所山崎剛史様に大変お世話になりました。ありがとうございました。とくに、風洞実験を指導して頂いた千葉大学生物機械工学研究室・D3村山友太様に感謝の意を表します。
そして、わたしのポスターをご覧にいただき、たくさんの有益なコメントを頂いた皆様に感謝しております。また、鳥学会の運営の皆様、記念品をご提供いただいたモンベル様に感謝の意を表します。今大会を通じて、多くの示唆と刺激を得ることができました。皆様から頂いた貴重なご意見を踏まえて、今後研究を進めていきたいと思っています。
本研究はJST奨学金の支援を受けて実施しています。
研究の概略
鳥類の翼は「飛翔」という鳥類にとって最も重要な機能を司っています。その形態は各種の生態学的ニッチと関係し、操縦性能や飛翔速度といった機能に影響を与えると考えられます。先行研究で、羽ばたき飛翔において翼先端部 =hand-wingで生じた揚力と推進力が重要であることが示されており、翼先端の形態が飛翔機能と密接に関連すると考えられます。このような翼先端の形態として、翼端スロットの有無が注目されます。これまで、鳥の翼機能形態と飛翔に関してはたくさんの研究が行われていますが、翼先端の形質に集中してその飛翔性能との関係を解析することで、鳥類種間での翼機能の違いをより詳しく評価できると考え、研究を進めています。
本研究では、91種のさまざまな飛翔行動と生息環境をもつ鳥類について、飛翔性能に関わると考えられる翼先端形質を、Klaassen van Oorschotの提案した指数 E (Emarginate index) とTi (wingtip sharp index) で評価し、さらに、アスペクト比とセミランドマーク法で翼全体の形を評価しました。その上で、これらの翼先端形質、及び翼形質が鳥類の飛翔行動や生息環境と相関を示すことを確かめました。つまり、短距離飛翔の鳥の翼は短く、先端が丸く、スロットのある形である一方、滑空飛翔の鳥の翼は長く、先端が尖って、スロットのない形でした。また、セミランドマーク法によって、翼先端の輪郭において羽ばたき飛翔の翼と滑空飛翔の翼が大きく異なっていることが示されました。これらの結果から、飛翔を特徴づける翼の形態として、初列風切羽分散度合、つまり、翼に占める初列風切羽の範囲が新たな形質指標と提案できます。羽ばたき飛翔と滑空する種では、初列風切羽分散度合が大きく異なっていました。
さらに、初列風切羽分散度合が、なぜ飛翔行動と関係するのか、機能的に調べるために、PIV粒子画像流速法によって風洞実験を実施しました。その結果、高迎角の際に、羽ばたき飛翔する鳥の翼は初列風切羽分散度合が小さいにもかかわらず、この部分を含むhand-wingで渦を安定させることで空力性能を維持していることがわかります。一方、滑空飛翔の翼は初列風切羽分散度合が大きいのですが、空力性能は翼全体で保っていることがわかりつつあります。風洞実験については、まだ条件が安定しないなど、課題がたくさんありますが、たくさん実験をして良い結果を得られればと頑張っているところです。