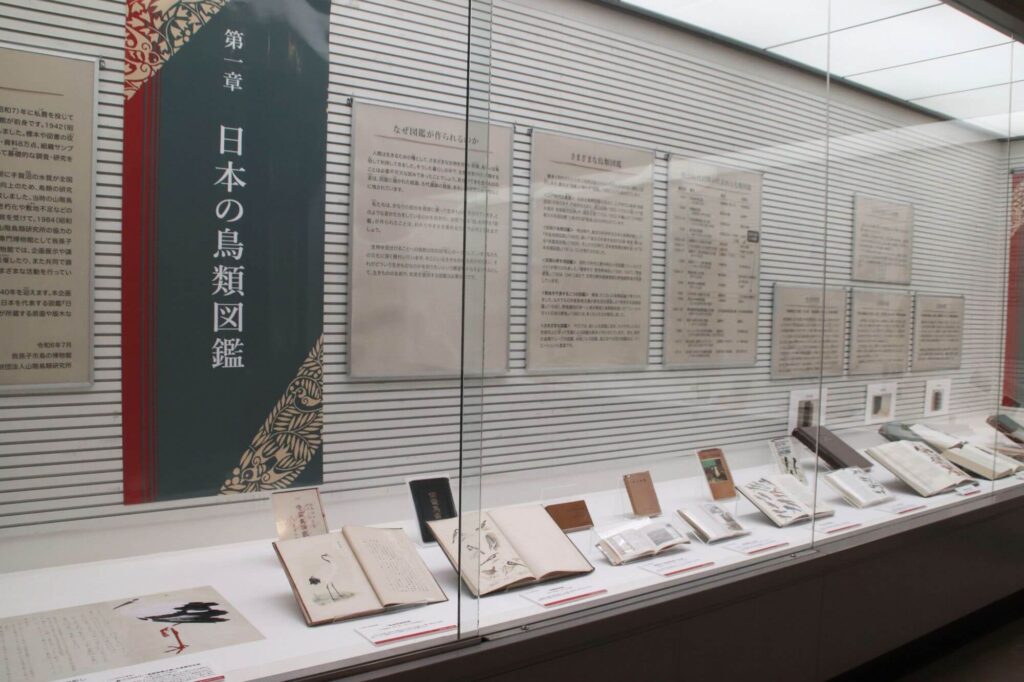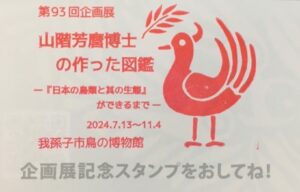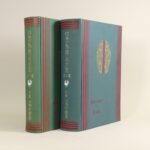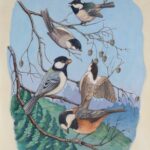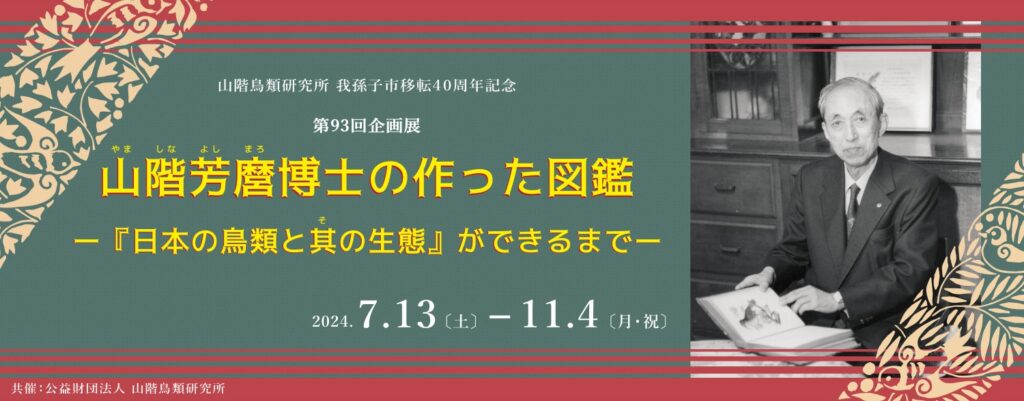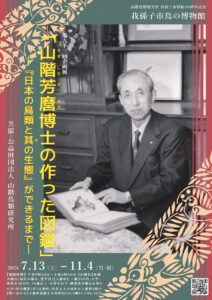浦 達也((公財)日本野鳥の会)
日本では過去100年間に1,000 km2 以上の湿地や草原が失われ,湿地や草原の乾燥化や埋立て,植生遷移による疎林化や樹林化,工業地域や農地,宅地への転用,最近は太陽光発電施設の設置などにより草原性鳥類の個体数が著しく減少していると言われる.近年,研究者や自然保護団体が国に働きかけたことにより,シマアオジ,シマクイナ,アカモズ,チュウヒなどの草原性または半草原性の鳥類が「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (種の保存法)」の「国内希少野生動植物種」に指定された.
種の保存法は,個体の取引規制,希少種の生息地保護や保護増殖に関して重要な法律である.しかし,希少野生動植物種の指定種やその生息地が適切に保護されているかは不明な点が多い.
そこで本集会では,国内希少野生動植物種に指定された草原性希少鳥類について,最近の生息状況等に加え,その種が指定された背景と指定後の種を取り巻く状況の変化について報告した.また,日本で希少鳥類が国内希少野生動植物種に指定されることの意義と,指定された鳥類に関する保護上の課題を確認し,今後,種の保存法が真に希少鳥類の個体や生息地を保護に貢献する法律にすべく,米国の種の保存法 (ESA: Endangered Species Act)と比較しながら議論した.
1.シマアオジの現状と国内希少野生動植物種指定
葉山政治((公財)日本野鳥の会)
シマアオジは旧北区北部の草原で普通にみられた種で,繁殖地もカムチャツカからフィンランドまで広がっていたが,1980年代以降は急激な繁殖地の縮小と約90%の個体数の減少が確認された.環境省レッドリストでは 2007年に CR (絶滅危惧IA類),2017 年には国際自然保護連合 (IUCN)のレッドリストでCRに選定された.また2017年には国内希少野生動植物種に指定された.しかし,国内での繁殖つがい数の減少は継続している.
減少要因としては,国外の渡りの中継地における違法な捕獲や越冬地となる農地環境の変化が指摘されている.シマアオジの回復のために種の保存法の下では国内でできることは少ない.
しかし,国内希少野生動植物種に指定されたことで,重要な繁殖地や中継地のあるロシアや中国との二カ国間渡り鳥保護協定等の場での情報交換や保護の必要性の共有が行われた.その結果,中国では保護対象種へ指定されたことで,日中両国でモニタリングが行われている.渡り性の種では多国間モニタリングの体制が必要であり,国内希少野生動植物種の指定がこの取り組みを促進することを期待する.
2.シマクイナの現状と保全状況
先崎理之(北海道大学大学院・環境科学院)
シマクイナは極東に分布する全長約15 cmの世界最小のクイナ科鳥類である.世界の生息個体数は少なく,減少していると思われることからIUCNのレッドリストではVU (危急種)に,環境省レッドリストでは絶滅危惧種IB類に選定されている.本種は日本では稀な冬鳥とされていたが,北海道と青森県の湿地で繁殖しており,関東以南の低地で越冬していることが近年明らかになり,2020年2月に国内希少野生動植物種に指定された.一方,我が国における本種の保全は,国内希少野生動植物種への指定の前後で特に変化はなく,前進していない.例えば,北海道の主要繁殖地である勇払原野や釧路湿原では,本種の繁殖確認前から国指定鳥獣保護区等であり,その他の生息地は保護区ではない.越冬地も耕作放棄地等の開発の脅威にさらされた土地に集中しており,しばしば開発により消失している.個体数の少ないシマクイナの保全には,繁殖地や越冬地の双方で生息地の保全を進めていくことが重要である.
3.アカモズの現状と国内希少野生動植物種指定
北沢宗大(国立環境研究所)
過去 100 年間で亜種アカモズの国内の繁殖分布面積は約90%減少し,現存する個体数は300個体未満である.このような危機的状況により,本亜種は2020年に国内希少野生動植物種に指定された.本亜種の保全活動の取り組みは,環境省の生物多様性保全推進交付金等により,市町村および動物園が主体となった生息域内外の保全事業が実施されているほか,関係者の献身的なモニタリングが各地で実施されている.これらの活動によって,アカモズの現状と直近の脅威となる要因が把握されており,また保全体制の確立が進みつつある.しかしながら,現行の活動体制が資金的にも,人手不足の観点からも持続可能ではないこと,また,種の保存法の効力が及ばない国外の越冬地および中継地の状況把握が進んでいないことが主要な課題となっている.関係者の尽力により,活動の輪は広まっているものの,依然として亜種アカモズが絶滅の脅威にさらされている状況が続いている.
4.オオセッカの現状と保全の問題
高橋雅雄(岩手県立博物館)
オオセッカは日本国内の生息個体数が約3,000羽と推定され,種の保存法の施行当初から国内希少野生動植物種に指定されている.東北地方北部の岩木川河口,仏沼,大潟草原,関東北部の利根川下流域,渡良瀬遊水地の計 5か所の湿性草原で繁殖するが,繁殖個体数の大多数を占める仏沼と利根川下流域では近年は減少傾向が続いている.越冬地は東北地方から九州地方で,東北地方 (福島県浜通り),関東地方 (利根川下流域,房総半島,渡良瀬遊水地),中部地方 (紀伊半島東部),九州地方 (薩摩半島)に多い.保全の問題として①湿性草原の植生環境の維持と②耕作放棄地への依存が挙げられ,①は乾燥化や疎林化などの湿性草原環境の劣化を防止し環境を回復させるために,繁殖地での火入れ,刈り取り,水位調整等の人為的管理が試みられている.②は特に越冬期で著しく,管理放棄や太陽光発電所建設による湿性草原環境の劣化や消失が進行している.
5.チュウヒの現状と国内希少野生動植物種指定
浦 達也( (公財)日本野鳥の会)
チュウヒは北海道の湿地を中心に,本州の一部の埋立地等で繁殖する,推定繁殖つがい数が140つがいとされる希少猛禽類である.環境省により2017年に国内希少野生動植物種に指定されたが,湿地の乾燥化や疎林や樹林化による営巣環境の劣化や減少,太陽光発電所の建設や圃場整備などの開発行為,作為または不作為による繁殖地への人の接近により,近年も繁殖個体数が減少していると考えられる.一方,国内希少野生動植物種に指定されて以降,開発行為時にチュウヒの繁殖の有無が気にされるようになった.チュウヒが繁殖している場合には,工事開始時期を繁殖期終盤に遅らせるなどの保全措置が講じられるようになり,繁殖阻害を受ける事例が減少してきている.
ヨシ原に生息するサンカノゴイもまた,近年は繁殖個体数の減少が危惧される種である.そこで日本野鳥の会が 2020–2022年に全国で繁殖するサンカノゴイの個体数を現地調査やアンケートおよび文献調査を経て数えた結果,17羽しかいないことが分かった.
6.草原性希少種と種の保存法
髙橋満彦(富山大学・教育学部)
種の保存法の概要を解説し,草原性希少鳥類の保護への寄与について議論した.種の保存法には,捕獲や譲渡等の規制 (個体等の取扱規制),生息地等保護区,保護増殖事業計画などのメニューが用意されているが,国内希少野生動植物種に指定されないと保護されない.国会の附帯決議もあって,国内希少野生動植物種の指定は増加しているが,鳥類では生息地等保護区の指定はなく,保護増殖事業計画の策定も追いついていない.
そもそも,草原性鳥類の絶滅危機要因は乱獲ではなく,生息地の保全が重要なので,希少野生動植物種に指定されても,捕獲等の規制だけでは守れず,生息地等保護区の指定や,保護増殖事業の展開が必要である.それでも種の保存法だけでは限界があり,他の法律による保全の展開,農政や河川行政との連携も考えなければならない.さらに,野焼き規制の見直しや,草原バンクなどの新しい仕組みも模索しながら,草原の減少を食い止めなければならない.
7.コメント :「国内希少野生動植物種」指定に一喜一憂するなかれ
玉田克巳(北海道立総合研究機構)
本集会で焦点のあてられた草原性希少鳥類の6種は全て渡り鳥で,うち 4種は国外で越冬するものであった.国内希少野生動植物種への指定は種の保存法によって捕獲や譲渡が規制されるが,捕獲は鳥獣保護管理法によってすでに規制されている.発表では各種の深刻な状況が報告されたが,6種のうち4種は IUCNのレッドリストでNT (準絶滅危惧種)もしくはLC (軽度懸念種)であり,国際的にみて保全が必要な種にはみえない.国際的にこれらの種を保全していくためには,渡り鳥等保護条約や生物多様性条約の枠組みを活用することが賢明であるが,各発表者からは,この辺の取り組みについての説明がほとんどなかった.減少している渡り鳥の保護対策を進めることは,越冬地や中継地の国々にとっても生物多様性を守ることにつながるはずであり,東アジアの国々にとっても WIN-WINの関係になるため,この視点を持つことが大事だと思う.
会場の様子。法律をテーマとした集会にもかかわらず、多くの方にご参加いただいた。