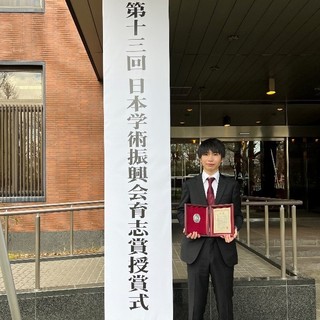海外での研究シリーズ、オーストラリアでの研究の様子を3回に分けて紹介していただいた天野達也さんの記事は、今回で最終回となります。天野さんは本記事でも触れられている研究内容で第18回学術振興会賞を授賞されています(授賞理由等詳細(PDF)|クイーンズランド大学のニュース記事)。
英語での論文執筆や発表で苦労されている方は多いと思いますし(私も現在オーストラリアにいますが、英語がペラペラになれる気はしません・・・)、英語ができて当たり前だから・・・と諦めてしまった経験がある人はいないでしょうか。その「当たり前」にあえて疑問を投げかける天野さんの論文を読むと、苦労しているのは私だけじゃないんだ、という気づきと、特に最後の考察と結論の文章、英語ネイティブの人たちに訴えかける力強い言葉に、英語を母国語としない世界中の研究者が勇気を貰える気がしています。是非、リンク先の論文にも(英語ですが、DeepLやGoogle翻訳など一昔前より飛躍的に向上している技術を活用しつつ)目を通してみてください。(広報委員 上沖)
連載の第一回ではオーストラリアへの異動の経緯を、第二回では私が感じたオーストラリアの研究・生活環境について書かせていただきました。
最終回となる今回は、私がオーストラリアに来てから立ち上げたtranslatEというプロジェクトについて紹介させていただこうと思います。
translatEプロジェクトでは、人によって母語が異なることによって生じるコミュニケーション上の障害、「言語の壁」に注目し、それが生物多様性の保全や、科学全体にどのような影響を及ぼすかを明らかにすること、またその問題を解消していくことを目的としています。詳しくはウェブサイトもご覧ください。
2008年に在外研究のために渡英して、当初は自分の言いたいことが全く英語で表現できなかった経験から、英語の壁の存在は個人的にずっと感じていました。ただし、その英語の壁が生物多様性保全や科学全体に及ぼす影響を意識するようになったのは、2011年頃にLiving Planet Index(LPI)に使われているデータの分布図を見たのがきっかけでした。アフリカのデータ分布が明らかにケニア、タンザニアなど一部の国に偏っていたのです。当時所属していた研究室の学生がこれらの国でのフィールドワークは英語が通じて便利と話していたこともあり、LPIのデータ分布と英語が公用語の国を見比べてみると驚くほど似通っていて、「英語が公用語の国のデータしか使われていない…?」と衝撃を受けました。
そこで生物多様性に関わる複数の国際的なデータベースを用いて、収蔵されているデータの分布と各国の英語話者数の割合を比較すると、やはりどのデータベースでも英語話者数の割合が高い国ほど収蔵されているデータ数も多いことが分かりました(Amano & Sutherland 2013)。

オーストラリア生態学会・国際保全生物学会オセアニア支部合同年次大会での発表

Ecological Society of Australia
このパターンが生まれる原因は二つ考えられます。一つは、英語が公用語でない国の方が実際にデータが少ないこと、もう一つは、英語が公用語でない国のデータが国際的に利用されていないこと、です。もちろん実際には両方影響しているのでしょう。ただ日本の研究やデータがしばしば日本語でしか得られず、国際的には使われにくいことを知っていた私としては、後者が少なくとも日本には当てはまることを知っていました。問題はそれが他の国にも当てはまるかでした。
そこで英語以外の言語でそもそもどのくらいの科学的知見が出版されているのか調べてみることにしました。幸い、非常に多くの国籍の研究者と知り合える環境にいたため、ターゲットとした16言語のほとんどについて、知り合いの中から文献検索に協力してくれる人を見つけることができました。フランス語は協力者がすぐには見つからなかった言語の一つで、受け入れ研究者だったビルに頼んだところフランス生態学会の会長(!)を紹介され、「フランス語でconservationは何というのですか?」と聞いたところ、「ええと… conservation… だね。」と返信が返ってきたのは今となっては笑い話です。
その結果、生物多様性保全に関わる文献の約3分の1は英語以外の言語で発表されている可能性が明らかになり、2016年に論文として発表しました(Amano et al 2016)。メディアでの取り上げられ方や研究者コミュニティからの反応に見るこの論文への反響は予想以上に大きく、もっと掘り下げてみる価値のある課題だと感じました。
そこでその後すぐ2017年から、各言語の話者から正式な共同研究者を募って、特定の基準に当てはまる学術論文が各言語でどのくらい存在しているかを明らかにする研究を始めました。当時所属していたグループが主導していたConservation Evidenceプロジェクトで生物多様性保全の対策の効果を科学的に検証した論文を検索・収集していたので、同じプロトコルを用いて、検索を他の16言語に拡張することで、同様の論文が英語以外の言語でどのくらい得られるかを明らかにすることにしました。
さらに2018年には言語の障壁が生物多様性保全に及ぼす影響として、世界規模でのエビデンス集約への影響(英語以外の言語で得られるエビデンスが国際的には利用されない問題)、また各地でのエビデンス利用への影響(英語でしか得られないエビデンスが非英語圏では利用されない問題)、という二つの問題に注目した研究計画をまとめ、獲得したfellowshipで2019年からオーストラリアへ移り、本格的なプロジェクトとしてこれらの課題に取り組むようになりました。

クイーンズランド大学セントルシアキャンパス
Fellowshipを獲得したことで、これらの研究に集中して取り組むことができ、言語の障壁が生物多様性保全に及ぼす影響について様々な成果を発表することができました。2021年には50人以上の共同研究者との3年以上にわたる共同研究の成果として、英語による保全対策の効果に関するエビデンスが少ない地域や種において、特に英語以外の言語で得られるエビデンスが多いという成果を発表することができました(Amano et al 2021a)。これはすなわち、英語以外で発表されている科学的知見を国際的に有効活用することで、英語だけでは情報が得られない種や地域について保全上重要な情報が手に入るということを示しています。

クイーンズランド大学セントルシアキャンパス
またNegret et al (2022)では、鳥類の絶滅危惧種では分布域内で特に多くの言語が使われていること、Chowdhury et al (2022)では、生物多様性保全に関わる文献の発表が英語だけでなく他の多くの言語でも毎年増え続けていることを示しました。どちらの結果も、言語の障壁を克服することが保全において重要であることを示しています。これらを踏まえてAmano et al (2021b)では、科学における様々なタイプの言語の障壁を克服するための解決策を提案しました。また以下の研究はまだプレプリントの段階ですが、英語が公用語でない国における生物多様性に関する報告書で英語以外の言語の文献が重要な役割を果たしていることを示した研究(Amano et al 2022a)、また日本を含む世界8か国、908人の環境科学者を対象とした調査によって、英語を母語としない研究者が被る不利益を定量化した研究(Amano et al 2022b)も発表することができました。博士課程の学生やポスドクと行っている研究も複数進行中です。
これら一連のプロジェクトの始まりはほんのちょっとした思いつきだったのですが、その後継続して取り組むことで、言語の壁という切り口から、エビデンスに基づいた保全や意思決定、科学コミュニケーション、学術界における不平等という問題など、様々なトピックに取り組みを発展させてくることができました。結果論ではありますが、その過程では、英国でのポスドク時代にあった、突拍子もないアイディアを実行に移す時間的・金銭的・精神的余裕、またこの研究でフェローシップが獲得できたことが示しているように、型にはまらない研究でも評価される環境が、それぞれ重要な役割を果たしていたと思います。また自分が重要だと思ったことに継続して取り組み、科学コミュニティ内外で機を見てその重要性を主張し続けることも、Conservation Evidenceプロジェクトを始め、様々な研究者の取り組みから学び、実行していることです。
今後もさらにプロジェクトを発展させ、生物多様性保全のために世界中で得られたあらゆる科学的知見が、言語や社会経済的背景に関わらず誰にでも利用できるような仕組みを実現していくために、少しでも貢献していければと思っています。

Centre for Biodiversity and Conservation Scienceのオフィス
translatEプロジェクト、及びクイーンズランド大学における私の研究グループKaizen Conservation Groupでは、共同研究者やJSPS海外特別研究員、また博士課程の学生として一緒に研究してくれる方を常に受け付けています。私達のグループはCentre for Biodiversity and Conservation Scienceという生物多様性保全を目標とした国際的にも著名な研究センターに属しており、様々な専門を持つ多くの研究者と交流することができます。興味のある方は是非ご一報ください。