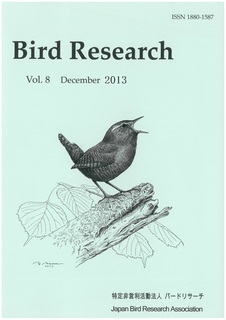原稿募集:口頭発表で質問をする際に、所属と名前を言うべきか?
広報委員長 三上修
鳥学会大会の口頭発表において、昔と違った慣習が広まり始めているのを感じる。何かといえば、口頭発表の発表に対して質問をする際、所属と名前をいう人が増えてきたということだ。たとえば、「○○大学の○○です。おもしろい発表をありがとうございました。ところで・・・」と質問を始めるのである。
私の気のせいでなければ、昔は、所属や名前を言うことはなかったように思う。そもそもなぜ、それを言う必要があるのだろうか。同じような疑問を持つ人はいるようで、ネットでみると、さまざまな意見がある。以下は、さまざまな分野の学会の方の意見を集約したものである。
名前と所属を言うのに肯定派の意見
・発表者は、所属と名を明かしているのだから、質問者もそれらを明かすのは礼儀。
・名乗ってもらうことで今まで論文でしか知らなかった研究者の名前と顔が一致するので、学術交流の場として学会を機能させる助けになる。
・名乗ることで、質問者をセレクションにかける(質問者にも覚悟をもってもらう)。
・発表者が質問者に連絡をとりたいことがあるので便利。
・セッション報告を書く人が後で困らない。
・妙な質問をする人を司会者がブラックリスト扱いできる。
否定派の意見
・知りたいのは質問の内容だから、そんなことに時間をかけず本題を早く言って欲しい。
・所属を言うのは、権威づけになってしまう。
・科学の質問には、所属や上下関係は不要だ。
中間派の意見
・所属は要らなくて、名前だけでいいのでは。
「セッション記事をまとめないといけない」ような場合は、名乗りは有用だろうし、また学会によっては、「所属と名前を言ってから質問してください」と、決まっているところもあるようだ。純粋科学の分野の学会ほど、このあたりがいい加減らしく、「物理が一番ひどく、次に生物系がひどく、対して化学、工学、薬学、医学などは、きっちりしている」という意見も見られた。私は他の分野をよく知らないが、個人的経験からいえば、生物系においても、遺伝や発生関係の学会などは、わりかしきっちりしていたような記憶がある。
鳥学会に関してどうかというと、「名乗り」は少なくとも20年位前までは不要だったのだろう。規模が小さく、みんな顔見知りだからである。だが、学会の規模が大きくなってきて、そうも行かなくなってきたし、いろんな学会を経験している人が増えてきたので、「名乗り」をする人が出てきたのだろう。
私、個人の意見としては、質問時に所属や名前を言わない方が良いと思っている。なぜなら、私にとっては、誰が質問したかはどうでもよくて、発表内容やそれに対する答えを知りたいからである。それに、1つでも多くの質問、解答があると良いと思う方だからである。
実際に「名乗り」に、どれくらい時間をとられるかを、試しに言ってみると8秒ほどかかることがわかる。おおむね2分(120秒)の質問時間のうち6%を占める。2人が質問し、両者とも所属と名前をいえば、2分間の12%も占めてしまう。消費税の8%でも大きいと思うのに(でも、しかたないとも思っている)、12%は多すぎる。それから杞憂かもしれないが、所属が無い人の中には、質問をしにくくなっている雰囲気があったりしないだろうか。
このように、個人的には、「名乗り」は無い方が良いというのが本音のところだが、名乗りたいという人を規制するつもりはない。ただ、学会としては決めておいて欲しい。「そういったことに、決まりごとは作らない」と。
質問における「名乗り」は無い方がいいと言っておきながら、教員の立場として学生に指導する場合には名前を言うように義務付けている。なぜなら「名乗りが必要無い」と感じる人は、それがあっても許容できるが、「無ければ失礼にあたる」と感じている人にとっては、許容できないだろうからである。学生は、いろんな分野にいく可能性があるので、安全策を教えているわけだ。
「名乗り」の話をしたので、ついでに、拍手の話もしておこう。鳥学会の大会においても、発表の後に拍手がある年とない年があるのをご存知だろうか? 同じ年でも、A会場とB会場によって拍手があったり、なかったりすることもある。私の知っている先生は、拍手は「ブラボー」の意味だから、本当にいい発表のときだけすべきだ、とおっしゃっている方もいた。こういう違いを見るのも、大会の楽しみの一つかもしれない。
さて、いろいろ書いたが、この文章の目的は何かといえば、「こんなくだらないことでも掲載して構わない」ということです。あっ、遅くなりましたが、私は、2016年1月から、広報委員長になりました。基本、社会的に問題があるような発言でなければどんどん掲載していく予定でいます。固い意見は、日本鳥学会誌のフォーラムがありますので、そちらに集約し、こちらの鳥学通信では、もう少しやわらかい、または、即時性の必要な情報を掲載していこうと思います。
内容はなんでもかまいません。
自著の宣伝、自分の研究紹介、鳥学に関する行事連絡、技術的なこと、研究室紹介などなど。
みなさまからの原稿お待ちしております。